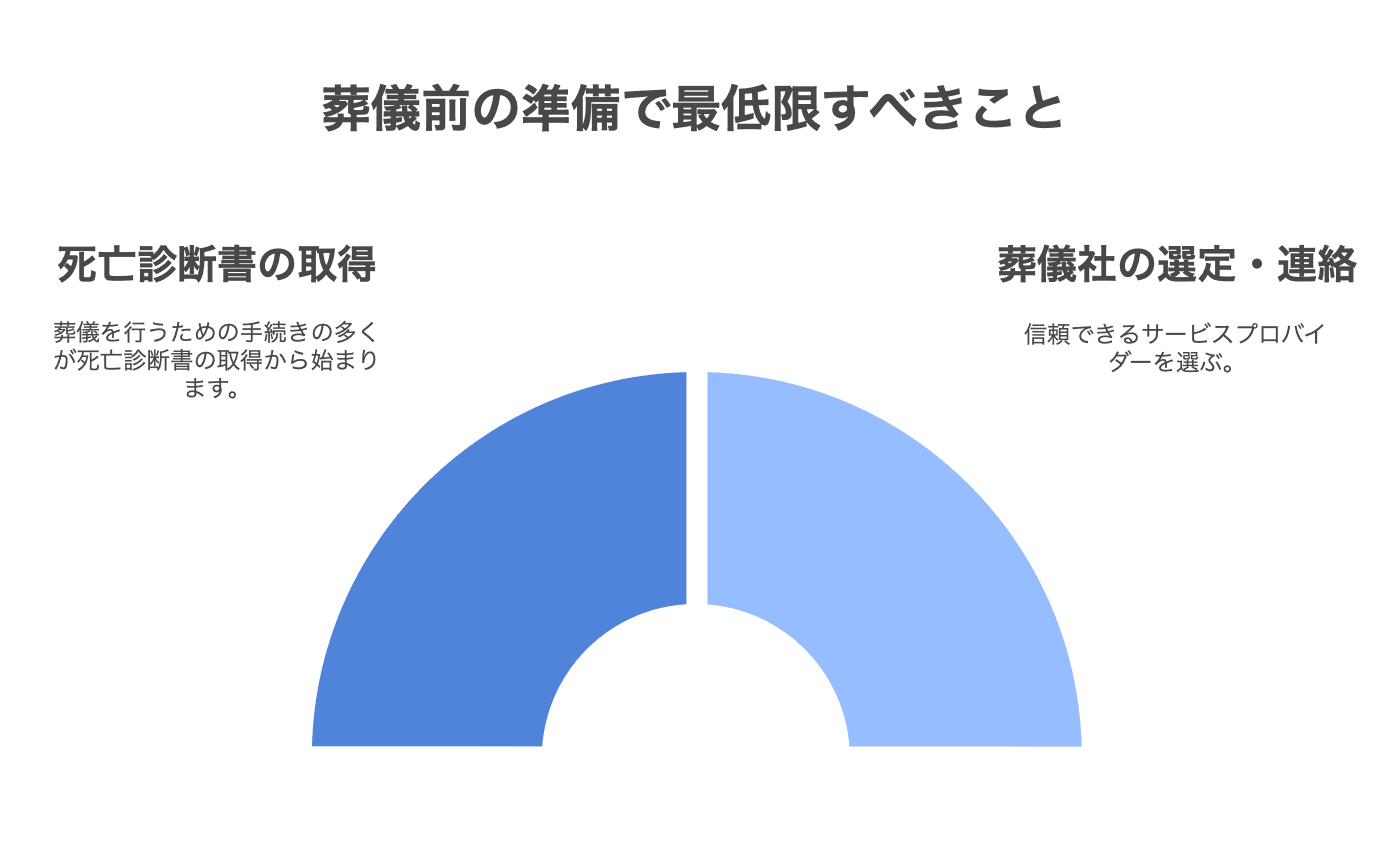葬儀を行うために必要なものと最低限すべきこと:流れや負担を軽減する準備方法まで完全ガイド
公開日: 更新日:
葬儀を行うために必要なものと最低限すべきこと:流れや負担を軽減する準備方法まで完全ガイド
葬儀を行う場面は、突然訪れることが多く、遺族にとって精神的にも体力的にも大きな負担となります。そのような状況の中で「何をすべきか」「どのように準備すればよいか」を知っているだけでも、葬儀の進行をスムーズに進めることが可能です。
本記事では、葬儀を行うために最低限必要なことから余裕があれば準備したいこと、逝去から葬儀までの具体的な流れ、さらに葬儀の負担を減らすための事前準備のポイントまでを詳しく解説します。
葬儀を行うために最低限すべきこと
葬儀を執り行うために、まずは必要な手続きや準備を進める必要があります。時間が限られる中で最低限行うべきことを以下にまとめました。
1. 死亡診断書の受け取り
故人が亡くなられた際、まず必要になるのが「死亡診断書」(生前に医師が診療していた傷病で亡くなった場合)または「死体検案書」(それ以外)です。この書類は葬儀や火葬の手続き、役所への届け出、さらに各種手続きにも欠かせない重要な書類です。
【死亡診断書の発行手順】
医師が発行:病院で逝去された場合、担当医師が死亡診断書を発行します。
検案書が必要な場合:自宅や事故現場で亡くなった場合は、警察の検死が必要になることがあり、医師による「死体検案書」が発行されます。
【死亡診断書の活用箇所】
役所への死亡届提出:逝去から7日以内に役所に届け出ます。多くの場合、葬儀社が代行してくれます。
火葬許可証の取得:死亡届提出後、火葬許可証が発行されます。
各種名義変更や保険請求手続き:金融機関や保険会社への届け出の際にも使用します。
2. 葬儀社の選定・連絡
葬儀の準備を進める上で、最も重要なのが葬儀社の選定です。葬儀社は、故人の搬送から安置、葬儀の手続きや式の進行を一括してサポートしてくれる頼れる存在です。早急に信頼できる葬儀社を選び、連絡を取りましょう。
【葬儀社を選ぶ際のポイント】
費用の明確性:葬儀にかかる費用が明確で、追加費用が発生しないか確認します。
葬儀形式への対応力:希望する形式(家族葬、一般葬、直葬など)や宗教儀式に対応可能かを確認します。
安置施設の有無:ご遺体を適切な環境で安置できる施設があるか確認します。自宅に戻す場合でも、搬送方法を相談しましょう。
【連絡時に確認する内容】
・故人の搬送手配(病院や自宅から安置施設への移動)
・葬儀形式や希望日程の相談
・安置場所の手配(自宅か安置施設か)
時間がかかる場合の対策
葬儀社選定に時間が必要な場合は、「搬送のみ」を専門業者に依頼する方法もあります。これにより、ご遺体を一時的に安置施設や霊安室に移すことが可能です。
余裕があれば準備しておきたいこと
最低限の手続きを終えたら、さらに余裕がある場合は以下の準備を進めておくと、葬儀当日の負担を大幅に減らせます。
喪主の決定
葬儀の主催者である喪主を決める必要があります。喪主は故人の配偶者や長男が務めることが多いですが、家族の事情に合わせて柔軟に決定できます。
葬儀形式の決定
以下のような形式の中から、故人や遺族の希望に応じた葬儀スタイルを選択します。
一般葬:親族・友人・知人を広く招く伝統的な形式。
家族葬:親族や親しい知人のみで行う小規模な葬儀。
直葬(火葬式):通夜や葬儀を行わず、火葬のみを行う形式。
形式によって必要な準備や費用が大きく変わるため、早めに決定することが大切です。
参列者リストの作成
葬儀に参列していただく方のリストを作成し、連絡手段を確保します。特に以下の点を意識して作成しましょう。
・故人の友人、知人
・遺族側の親族・知人
・会社や地域コミュニティの関係者
宗教や宗派の確認
宗教や宗派によって葬儀の進行方法や作法が異なるため、事前に確認が必要です。菩提寺がある場合は早めに連絡を取り、日程や準備物について相談します。
身内が急逝した際に参列者がする準備
急な訃報を受けた際、参列者として迅速に対応するには以下の準備が必要です。
1. 駆けつける先の確認
危篤時または逝去直後に駆けつける場合は場所を確認しましょう。病院に駆けつける場合は部屋番号まで確認しましょう。服装は平服でも構いません。
2. 必要なものの用意
参列に必要な物を用意します。
香典: 地域や慣習に応じた金額を準備します。香典袋の表書きも確認します。
数珠: 仏式の場合、数珠は必須アイテムです。
喪服: 黒を基調とした服装を用意します。控えめなアクセサリーや靴も選びましょう。
逝去から葬儀までの流れ
葬儀を進めるには、逝去後から火葬までの一連の手順をスムーズに進めることが重要です。ここでは、葬儀の準備を見据えた具体的な流れと、その際に考慮すべきポイントを解説します。
【逝去から葬儀までの流れ】
1. 逝去
流れ:医師から死亡診断書を受け取り、必要書類の準備を始めます。
準備:死亡診断書は役所への届け出や火葬許可証の取得に必須なので、速やかに手配しましょう。
2. ご遺体の搬送
流れ:葬儀社や搬送業者に連絡し、故人を安置場所へ移動します。
準備:安置先(自宅や葬儀社の安置所など)を選び、速やかに搬送手配を行います。
3. 葬儀社との打ち合わせ
流れ:葬儀の形式や規模、日程を葬儀社と相談し決定します。
準備:希望する葬儀形式や参列者の範囲、予算を事前に家族で話し合っておくとスムーズです。
4. 通夜・葬儀の実施
流れ:参列者を案内し、故人を偲ぶ儀式を執り行います。
準備:香典返しや会葬礼状、受付の準備を事前に整えておきましょう。
5. 火葬
流れ:火葬場で故人を見送り、遺骨を拾い上げて収めます。
準備:火葬許可証を忘れずに持参し、骨壺や納骨に関する準備も進めておきます。
葬儀の負担を減らすにはどのような準備をしたらいい?
葬儀は突然の出来事であることが多く、遺族にとって精神的・経済的な負担が大きくなる場合があります。しかし、事前に準備を進めておくことで、その負担を大幅に軽減することが可能です。
1. 生前の希望を確認する
故人が生前に葬儀について希望していた内容を確認しておくと、遺族の負担を軽減できます。エンディングノートや遺言書に記されている場合もあるので、事前に話し合いや確認を行いましょう。
【確認しておきたい内容】
・希望する葬儀の形式(家族葬、直葬、一般葬など)
・宗教的儀式の有無(宗派や祭壇の形式など)
・葬儀費用の予算や保険の利用可否
・弔問客の招待範囲や具体的な希望
・遺影写真の選定(本人の希望写真があるかどうか)
2. 葬儀費用の事前確認
葬儀費用は形式や規模によって大きく異なります。生前に費用の見積もりを取ることで、予算計画が立てやすくなり、遺族の金銭的負担を減らすことができます。複数の葬儀社から事前に見積もりを取得して比較することが重要です。
【葬儀費用の目安】
直葬(火葬式):20~30万円
家族葬:50~100万円
一般葬:150万円以上
また、葬儀保険を活用することで、予算の負担を軽減する方法もあります。保険に加入しておくと、急な支出に備えられます。
3. 必要書類のリスト化
葬儀後にはさまざまな手続きが必要です。これらをスムーズに進めるために、必要書類や手順を事前にリスト化しておきましょう。代表的な書類と手続きの例を挙げます。
【主な必要書類】
・死亡診断書:死亡届や火葬許可証の申請に必要
・火葬許可証:火葬時に必須
・健康保険証の返却書類
・年金や保険の手続き関連書類
・銀行口座解約や名義変更の書類
手続きに時間がかかる場合もあるため、各書類のコピーを用意しておくと便利です。
4. 信頼できる葬儀社の選定
葬儀の負担を減らすには、信頼できる葬儀社を選定しておくことが重要です。事前に地元の葬儀社の評判やプラン内容を調査し、候補をいくつかリストアップしておきましょう。
【選定時のポイント】
・料金プランの明確さ(追加費用が発生しないか)
・サポート内容(書類手続き代行、参列者対応など)
・遺族の希望を尊重した柔軟な対応が可能か
5. 親族間での話し合い
家族間で葬儀の形式や進行について事前に話し合い、共通認識を持っておくことが大切です。費用分担や弔問客の範囲についてもあらかじめ合意しておくと、当日のトラブルを防ぐことができます。
【話し合いのテーマ例】
葬儀の規模と形式
弔問客の範囲(親族のみ、友人知人も含むなど)
葬儀費用の分担方法
故人の遺志をどのように反映するか
6. エンディングノートの活用
エンディングノートは、故人が生前に希望する葬儀内容や相続に関する情報を記録するためのツールです。遺族が迷うことなく故人の意志を尊重した対応ができるため、負担軽減につながります。
【エンディングノートに記載する内容】
・葬儀の希望内容(形式、宗教儀式の有無など)
・連絡してほしい人のリスト(親族や友人、関係者)
・資産や重要な書類の保管場所
・その他、故人からのメッセージ
おすすめのエンディングノートについて紹介した記事もありますのでぜひ参照してみてください
まとめ
葬儀を行う際には、まず死亡診断書の受け取り、ご遺体の搬送、葬儀社の選定、ご遺体の安置といった最低限の手続きを進める必要があります。それに加え、喪主の決定や葬儀形式の検討、参列者リストの作成などを進めておくと、当日の負担が大幅に軽減されます。
また、負担を減らすためには、葬儀費用の事前確認や生前の希望を聞いておくことが非常に有効です。信頼できる葬儀社を選び、事前に相談しておくことで、より安心して故人を送り出すことができるでしょう。
この記事を共有
他の人はこんな記事も見ています

正月や年末に亡くなったらどうする?年末年始の葬儀の流れと進め方
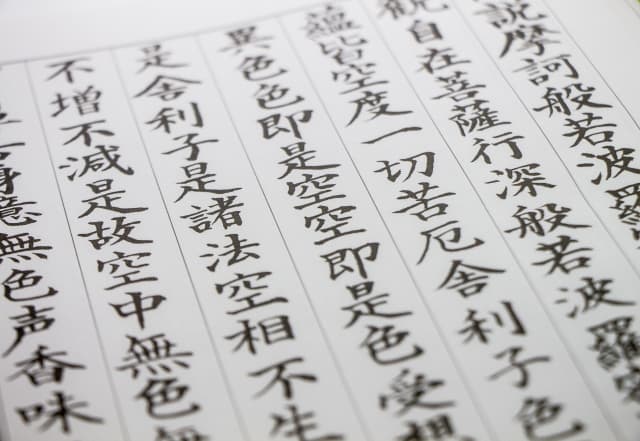
「般若心経」とは何か?意味をやさしく解説|全文・読み方・現代語訳つきで初心者でもわかる仏教の智慧

ペット用の棺は必要?心を込めて送り出すための完全ガイド|素材選び・サイズ測定・手作り方法から安置・副葬品まで徹底解説

タワーマンション節税とは?2024年以降の新ルールと有効な活用法を解説

相続した家が競売にかけられそうなときに知っておくべき対処法|理由と回避策を徹底解説

サブリース契約は相続対策になる?知っておくべき注意点と活用法
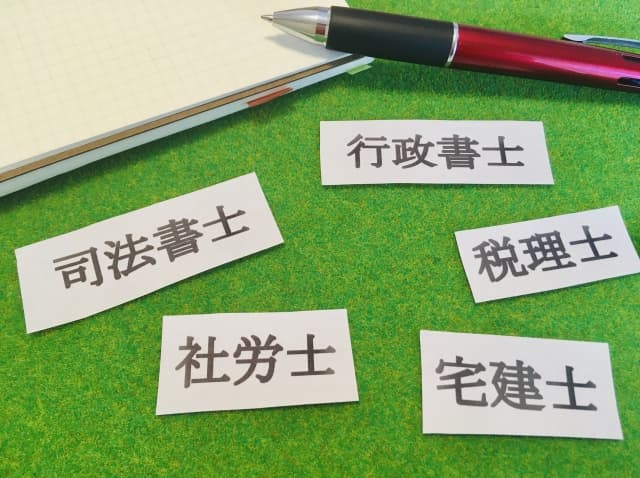
士業とは?8士業・10士業の違いと職種一覧をやさしく解説

代襲相続とは?孫や甥・姪が相続人になる場合と注意点をわかりやすく解説