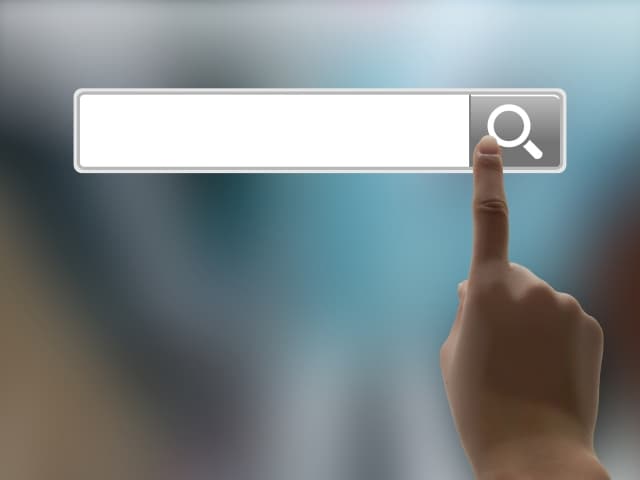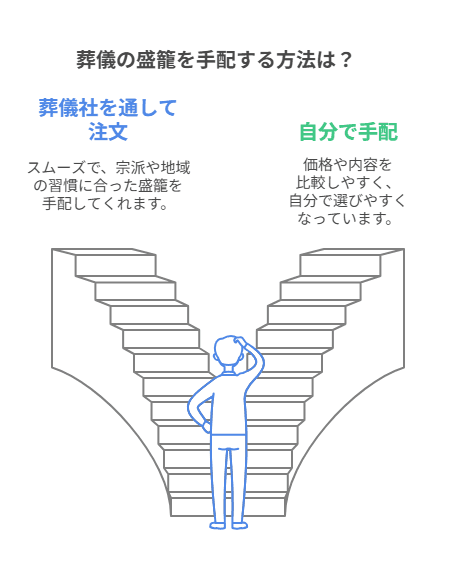盛籠とは?宗教別の違いから贈り方・マナー・費用まで徹底解説
公開日: 更新日:
大切な人を見送る葬儀の場では、故人への敬意や遺族への哀悼の意を表すために、様々な供物が用意されます。その中でも「盛籠(もりかご)」は、果物や食品などを籠に美しく盛り付けたお供え物として、特に目を引く存在です。
しかし、盛籠の中身や贈り方には宗教や地域の習慣によって違いがあり、正しいマナーを知らずに送ってしまうと、かえって失礼になる可能性もあります。例えば仏教では果物や乾物が定番ですが、キリスト教ではそもそも盛籠という文化自体がないこともあります。
また、葬儀の前に盛籠をどう準備すればよいのか、どの程度の費用がかかるのか、送るときのタイミングや注意点など、意外と知られていない点も多くあります。盛籠は「心を形にして届ける」ものだからこそ、正しい知識と配慮が求められるのです。
この記事では、盛籠とは何かという基本から、宗教ごとの中身の違い、準備方法や費用、贈る・受け取る際のマナーまでを詳しく解説します。実際の葬儀の場で恥をかかないために、そして遺族への思いやりをきちんと届けるために、ぜひ最後までご覧ください。
盛籠(もりかご)とは
盛籠(もりかご)とは、葬儀や法要の際に、故人の霊を慰めるために供えられる供物(くもつ)の一種で、果物、缶詰、乾物、菓子などを美しく籠に盛り込んだものを指します。「盛り籠」「盛かご」と表記されることもありますが、いずれも同様の意味を持ちます。
盛籠の役割と意味
盛籠には、単に食べ物を供えるという以上に、「供養の気持ちを形にして表す」という役割があります。故人の生前の好物や、保存がきき長持ちする食品を選ぶことが多く、「亡くなった方があの世でも不自由しないように」という願いも込められています。
また、遺族にとっては、弔問客からの心のこもった贈り物として、精神的な支えになることも多いです。形式美と実用性が融合している点で、日本ならではの丁寧な供養文化の象徴とも言えるでしょう。
誰が贈るのか?
盛籠は、一般的に親族、友人、知人、会社関係者など、故人とつながりのある人が贈ります。特に企業や団体から贈られるケースでは、企業名入りの名札を添えることで、社会的関係を示す役割も果たします。
ただし、贈るかどうかは必須ではなく、最近では「香典だけにする」「供花を選ぶ」という選択肢も増えています。重要なのは「形式にとらわれず、気持ちを表すこと」です。
宗教で変わる盛籠の中身とは?
盛籠の中身は、単に食品を詰めたものではなく、宗教や宗派の教義や習慣に基づいて選定されることが多くあります。そのため、宗教ごとの違いを理解しておかないと、思わぬ失礼になる可能性もあります。以下では、代表的な宗教である「仏教」「神式(神道)」「キリスト教」の3つについて、盛籠の内容の違いを詳しく解説します。
仏教
日本の葬儀で最も多く行われているのが仏教式です。仏教における盛籠の中身は、以下のような品物が定番とされています。
・果物(りんご、みかん、バナナなど):日持ちし、彩りも良いため
・乾物(昆布、椎茸、海苔など):保存性が高く、縁起の良いもの
・缶詰や瓶詰(フルーツ、ジュース、佃煮など)
・菓子類(カステラ、せんべいなど)
仏教では「五供(ごく)」という供養の基本概念があり、香・花・灯明・飲食・浄水の5つを供えることが理想とされています。盛籠はこのうち「飲食」の要素を象徴するものであり、故人への敬意を込めて丁寧に選ばれるのです。
神式(神道)
神道の葬儀である「神式」では、仏教のように明確なルールが少ない反面、「清浄であること」が非常に重視されます。そのため、盛籠の中身や包装にも独特の配慮が必要です。
・白を基調とした包装・装飾
・「奉献」と書かれたのし紙を使用
・果物や白い菓子類(白餅など)を選ぶことが多い
また、神道では死を「穢れ(けがれ)」とする考え方があるため、供物の内容も仏教より控えめであることが一般的です。迷った場合は、葬儀を取り仕切る神社や葬儀社に事前確認するのが安心です。
キリスト教
キリスト教では、仏教や神道のような供物の文化があまり存在しないため、盛籠を贈ることは一般的ではありません。むしろ、供花(生花)やカード、献花などが主流です。
とはいえ、日本国内では「慣習として」盛籠が贈られる場合もあるため、その場合は以下の点に配慮することが大切です。
・過度な装飾を避ける
・十字架やキリスト像など宗教的モチーフを含まない
・必ず遺族の意向を確認した上で手配する
キリスト教式の葬儀では、「心を込めた言葉」が何より重視されます。形式的な供物よりも、お悔やみの手紙やカードの方が喜ばれることも多いため、ケースに応じた対応が必要です。
葬儀で盛籠を用意する方法
盛籠を準備するには、葬儀のスタイルや会場に応じた適切な手配方法を知っておくことが重要です。どこで、いつ、どのように用意すればよいのかを事前に理解しておけば、突然の訃報の際にも落ち着いて対応できます。
1. 葬儀社を通して注文するのが一般的
最も確実でスムーズなのは、葬儀を取り仕切る葬儀社に直接依頼する方法です。葬儀社は、宗派や地域の習慣に合った盛籠を把握しており、参列者や弔問客の立場に応じた適切な内容・サイズ・タイミングで手配してくれます。
多くの場合、葬儀社が取り扱っている提携の花屋やギフト会社が盛籠を作成・搬入するため、事前に式場へ直接送ることができ、当日の混乱を避けられます。
2. 自分で専門業者に手配することも可能
最近では、オンラインで盛籠を注文できるサービスも増えています。例えば「葬儀 盛籠 手配」などのキーワードで検索すれば、宗派や会場に応じたセットを選べる専門サイトが多数見つかります。
この方法のメリットは、価格や内容を比較しやすいことと、ポイント還元などのネット独自の特典があることです。一方で、式場によっては「外部からの供物持ち込み不可」の場合もあるため、必ず事前に会場や葬儀社へ確認しましょう。
盛籠を注文するタイミング
盛籠は、通夜または葬儀当日に会場へ届くように手配します。突然の訃報で時間がない場合でも、迅速に対応できる業者が多くあります。
とはいえ、人気のある日時や大規模な葬儀では搬入が混み合うこともあるため、できる限り早めに手配することが推奨されます。
盛籠のご用意にかかる費用
盛籠の費用は、注文方法や中身のボリュームによって幅がありますが、まず押さえておきたいのが一般的な全国相場の目安です。
一般的な盛籠の価格相場
日本全体で見た盛籠の価格帯は、およそ7,000円〜30,000円。特に多く選ばれているのは10,000円〜15,000円前後の中価格帯です。これは個人でも法人でも使いやすく、マナー的にも無難とされる価格帯です。
価格帯 | 想定される用途 | 選ばれる傾向 |
|---|---|---|
~10,000円 | 家族葬や個人での弔問 | シンプル・小型 |
10,000〜15,000円 | 一般的な葬儀(親族・友人) | 最も選ばれるゾーン |
15,000〜25,000円 | 法人・団体からの贈答 | 社名入り・中型〜大型 |
25,000円以上 | 社会的立場が高い方・特別な関係 | 豪華・高級タイプ |
1.葬儀社に依頼する場合の費用と特徴
最も一般的な方法は、葬儀社を通じて盛籠を手配することです。宗教・地域性への配慮や会場搬入の調整なども一括で任せられるため、安心感があります。
費用の目安(葬儀社経由)
サイズ | 内容例 | 価格帯(目安) |
|---|---|---|
小型 | 果物・乾物など | 約8,000〜12,000円 |
中型 | 果物+缶詰・菓子など | 約12,000〜20,000円 |
大型 | 高級詰合せ+装飾 | 約20,000〜35,000円 |
特徴
・宗教や地域の慣習を理解しているため安心
・搬入・設置・名札など一括対応
・急ぎの依頼にも対応可能な場合が多い
・価格は自分で手配するより1,000〜3,000円ほど高め
2. 自分で手配する場合の費用と特徴
インターネット通販や百貨店、ギフト専門店を活用して、自分で盛籠を選ぶ方法です。価格比較や中身のカスタマイズができ、コストパフォーマンスに優れています。
費用の目安(個人手配)
サイズ | 内容例 | 価格帯(目安) |
|---|---|---|
小型 | 果物や乾物のみ | 約5,000〜10,000円 |
中型 | 果物+缶詰や菓子など | 約10,000〜18,000円 |
大型 | 高級食材・セット | 約18,000〜30,000円 |
特徴
・価格重視・比較検討可能
・自分で内容を選べるため柔軟性が高い
・配送条件や名札対応は要確認
・会場によっては持込制限に注意
どちらを選ぶべきか?判断ポイントまとめ
項目 | 葬儀社に依頼 | 自分で手配 |
|---|---|---|
安心・確実性 | ◎(すべて任せられる) | △(確認必須) |
費用 | △(やや高め) | ◎(内容に対してお得) |
スピード | ◎(即日対応可) | △(余裕が必要) |
柔軟性 | △(選択肢限られる) | ◎(中身の自由度が高い) |
盛籠をお送りする際のマナー
盛籠を送る行為は、単なる物品の贈答ではなく、故人とご遺族への思いやりを形にした供養の一環です。適切なタイミングや宗教的配慮、礼儀を守ってこそ、気持ちが正しく伝わります。この章では、盛籠をお送りする際に注意すべきマナーを、わかりやすく解説します。
ご遺族に事前に確認する
盛籠を贈る前にまず大切なのは、「ご遺族が盛籠を受け入れているか」を確認することです。宗派や地域によっては、供物自体を辞退する場合もあり、勝手に送ることはかえってご迷惑になることもあります。
・通夜や葬儀の案内に「供花・供物辞退」と記載がある場合は送らない
・明記されていない場合でも、親族や葬儀社に確認を取るのが安心
これは最低限の礼儀であり、遺族の意向を尊重することが最も重要です。
お供え物と別に香典を用意する
盛籠はあくまで「供物」であり、「香典(現金)」とは別物です。したがって、盛籠を送るからといって香典を省略するのはマナー違反とされます。
・香典は香典袋に入れ、別途弔問時に手渡すか、郵送で送付
・盛籠と香典の両方を用意することで、形式と心情の両方を伝える
経済的な理由でどちらか一方に絞る場合は、香典を優先し、気持ちだけでも手紙で添えるなどの工夫が必要です。
辞退された場合は無理に送らない
最近では「家族葬」や「密葬」のように、供物や香典を一切辞退するスタイルも増えています。ご遺族がそのような意向を示した場合、無理に送ることは礼を欠く行為となります。
・辞退された場合は、手紙やメッセージカードで気持ちを伝える
・無理に送ってしまうと、受け取りや返礼の手間をかけてしまうことに
本当に思いやりがある人ほど、贈ること以上に「贈らない配慮」も大切にします。
盛籠を受け取った際のマナー
盛籠は、遺族が故人に代わって受け取る「供養の贈り物」です。正しいマナーを守りつつ、贈ってくださった方への感謝の気持ちをきちんと伝えることが大切です。ここでは、受け取った後の対応、飾る期間、中身の扱いまでを一括で解説します。
受け取り時の基本マナー
盛籠は、通夜または葬儀の当日までに式場へ届くように手配されるのが一般的です。受け取る際は、以下のような点に注意します。
・名札を確認し、贈り主の名前を控える
・破損や誤配がないかチェック
・不明点があれば、すぐに葬儀社へ相談
葬儀社によっては、搬入・設置・飾り付けまでサポートしてくれることが多いため、安心して任せられます。
盛籠を飾る期間
盛籠は、一般的には通夜から葬儀当日までの間、祭壇の周囲に飾られますが、宗教や地域の慣習によっては「初七日(しょなのか)」まで飾ることも多いです。
・初七日は、故人が仏前に赴く最初の節目とされる大切な日
・それまではお供え物として飾り、故人への祈りを続ける意味がある
・葬儀後すぐに片付ける場合もあるため、葬儀社と相談のうえ決定
果物や食品が主な中身となるため、衛生管理の面からも1週間程度が実用的な目安とされています。
中身の扱い
葬儀後、盛籠の中身は多くの場合、遺族や近しい親族で分け合って持ち帰るのが通例です。
・果物や菓子、乾物など、賞味期限があるものはすぐに消費できるよう小分け
・包装されている個別パッケージ品が多く、分配しやすい
・希望があれば参列者におすそ分けするケースもあり
また、場合によっては福祉施設や地域の支援団体へ寄付されることもあります。中身の活用については、遺族の判断と地域の慣習に合わせて柔軟に対応されます。
贈り主への対応とお礼
盛籠は、心のこもった供物ですので、贈ってくれた方への感謝は丁寧に伝えることが望ましいです。
・葬儀中に名前を紹介する(司会者が読み上げることも)
・後日、香典返しにお礼状を添えて対応
・特別に関係の深い方には、手紙や電話で直接お礼を
まとめ
盛籠(もりかご)は、故人への敬意と遺族への哀悼の意を込めて贈る供物です。その中身や贈り方には宗教や地域による違いがあり、正しいマナーと配慮が求められます。仏教では果物や乾物、神道では清浄を意識した白を基調とした品、キリスト教では盛籠自体を贈らないこともあります。
盛籠の費用は5,000円〜30,000円程度が一般的で、葬儀社に依頼するか自分で手配するかで価格や対応も異なります。通夜から葬儀、初七日まで飾ることが多く、葬儀後は中身を親族で分け合うのが慣例です。
送る際は遺族の意向を確認し、辞退されている場合は無理に贈らないことが礼儀です。また、香典とは別に用意し、受け取ったら記録を残して感謝を丁寧に伝えることも忘れてはなりません。
盛籠は形式だけでなく、心を込めて故人と遺族に寄り添う供養の手段です。正しい知識とマナーをもって贈ることで、その思いがきちんと届くはずです。
この記事を共有